![]()
ー 9例の検討 ー
はじめに
経口移行に関するこれまでの研究では,1~2例の報告はあるが多数をまとめたものはなかった.当院は100床の療養病床を有し,開院して7年目である.当初から胃瘻患者が経口摂取能力を取り戻すよう,各職種が協働し積極的に取り組んできた結果,9例が成功した.その内容と結果を検証したので報告する.また,経口摂取能力の回復に伴い,他のADLも顕著に改善した症例を紹介する.
Ⅰ.研究目的
9例の成功例より,胃瘻から経口摂取に移行できる要因を探る.
Ⅱ.研究方法
1. 期間および対象
平成13年10月から訓練を開始し,18年10月までに胃瘻から脱却して,経口摂取が可能になった患者9名(男性3名,女性6名).
2. 調査方法
以下の9項目について比較検討した.1)年齢,2)胃瘻造設の理由,3)藤島のグレードによる嚥下造影(VF)所見,4)胃瘻造設から摂食機能療法 (以下訓練と略す) 開始までの期間,5)訓練の手順(食形態など),6)訓練開始から3食経口摂取までの期間,7)3食経口摂取から胃瘻チューブ抜去までの期間,8)意思疎通の有無,9)自力摂取の有無,である.
*藤島のグレードについて簡単に紹介する.
1:嚥下困難または不可.嚥下訓練適応なし
2:嚥下困難または不能.基礎的嚥下訓練適応あり
3:摂食訓練可能
4:楽しみとしての摂食は可能.栄養摂取は非経口
5:一部(1~2食)栄養摂取が経口から可能
6:3食とも栄養摂取が経口から可能だが,補助栄養の併用が必要
7~9:嚥下障害軽度で,栄養摂取は経口から可能
10:正常の摂食・嚥下能力
3.症例紹介
経口摂取が進むにつれ,ADLが顕著に改善したI氏について呈示する.
4.倫理的配慮
症例の情報および写真の使用に関しては,文書で承諾を得た.
Ⅲ.結果
1.対象(表1)
| 表1 対象患者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.検討項目(表1)
1)平均年齢は87.7歳,90歳以上が3名,最高は96歳であった.
2)胃瘻造設の理由では誤嚥性肺炎が7名を占めた.
3)VF結果は藤島のグレードの2が4名,3が1名,4が3名,5が1名であった.
4)胃瘻造設から訓練開始までの期間(図1)は最短2ヶ月,最長2年8ヶ月と大きな差があった.
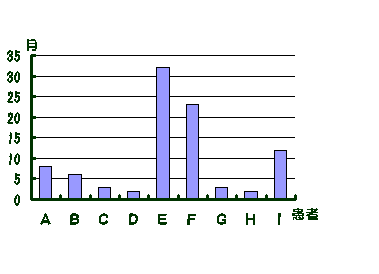 |
| 図1 胃瘻造設から訓練開始までの期間 |
5)食形態については,通常は嚥下機能の回復状況に合わせて段階的な訓練食を使用するが,G氏の場合は,本人の希望で最初から主食をおにぎりとし,副菜のみ段階的に進めた.
6)訓練開始から3食経口摂取までの期間(図2)は半月から1年10ヶ月と,これも大きな差があった.
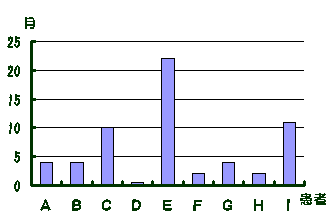 |
| 図2 訓練開始から3食経口摂取までの期間 |
7)3食経口摂取から胃瘻チューブ抜去までの期間(図3)は0~12ヶ月とこれも大差がみられた.
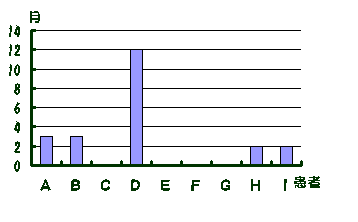 |
| 図3 3食経口摂取から胃瘻チューブ抜去までの期間 |
8)意思疎通については,全員が介助者の声掛けや簡単な指示を理解できた.
9)食事動作については9名中8名が,3食経口摂取の段階で自力摂取できた.
3.症例紹介
I氏は,87歳女性,認知症の方である.平成16年10月に他の病院で胃瘻造設され,約1年後に当院に入院された.当院入院前は1日中ベッド上生活で,ADLは全介助であった.入院時は,要介護度4,認知度Ⅳ,生活自立度B2であった.VF所見はグレード2で間もなく訓練を開始した.
食事摂取状況および行動の変化について述べる.
17年10月:まずSTがかかわってアイスクリームなどのおやつを開始したが,ときどきムセがみられ,食べることに対する積極性はあまりみられなかった.言葉掛けに対して簡単な返答はあったが,笑顔はみられなかった.
18年1月:毎日,ソフティア茶とペースト食のおやつを自力摂取するようになり,交互嚥下を指導した.この頃,風船バレーが上手で,他のレクリエーションにも積極的に参加され,入浴時自分で服を着ようとされるなどの変化が現れた.
3月:経口から1日1回,昼食に粥ゼリーとトロミつきミキサー菜をムセなく上手に食べられるようになった.病棟の廊下を車椅子で自操され,車椅子⇔ベッド移動が可能になった.また,入浴時には自分で体を洗われるようにもなった.
4月:経口摂取が1日2回に増え,粥ゼリーとソフト菜を通常の半分量食べられるようになった.会話や笑顔が増え,歌を歌われることもあった.
8月からは経管栄養が中止となり、3食経口摂取となった。そして、トイレ誘導時は,尿意の有無をはっきりと意思表示されるようになった.
 |
 |
| 写真1 食事摂取 |
写真2 車椅子自操 |
写真1は7月に撮影した昼食場面である.粥ゼリーとソフト菜,ソフティア茶をスプーンで上手に全量摂取され「おいしかった」と言われた.
写真2は車椅子を自操されトイレに向かわれた時に撮影した.職員が声をかけることもあるが,自分から「トイレに行きたい」と言われ,トイレで排尿できている.そして,訓練開始から約1年後の18年10月に胃瘻抜去となった.
Ⅳ.考察
栄養は生命の源であり,口から摂取できない場合の最終手段は胃瘻栄養であると考えられていた.しかし,少数ではあるが再び経口摂取に移行できる症例があることもわかってきている.
私たちが経験した9例の成功例からいえることは,
1 年齢に上限はほとんどない.90歳以上の高齢であっても,条件を満たせば訓練を開始すべきである.
2 胃瘻造設は,嚥下障害や誤嚥性肺炎を繰り返す症例に適用されることが多く,訓練に際しては,医師およびSTによるVFの判定が不可欠である.また,訓練中の誤嚥性肺炎を予防するためには,日常的な口腔ケアが大切であり,当院では歯科衛生士・看護師・介護士が協力して1日3回の口腔ケアを実施している.また,味覚や食感を引き出すためにも,口腔ケアにより,正常で清潔な口腔機能を維持・向上させる必要がある.
3 胃瘻造設から訓練開始までの期間をみると,最長2年8ヶ月であった.経口摂取中止期間が長いと廃用症候群が進行し,胃瘻からの脱却が困難になると思われるが,E氏・F氏の結果から2年前後であれば経口摂取能力は回復できると考える.
4 訓練開始から3食経口摂取までの期間や,3食経口摂取から胃瘻チューブ抜去までの期間は,個人差が大きかった.後者は,水分が円滑に摂取できるかどうかの影響が大きいと考えられたが,いずれにしても,短期間であきらめず根気よく訓練を継続することが大切である.
5 訓練食は,「棒付飴」「アイスクリーム」などから開始し,通常はゼリー食,ペースト食,ソフト食へと進める.当院では栄養士と相談しながら,同じゼリー食でも固形に近いものから流動に近いものまで対象にあわせて提供している.しかし,G氏はアイスクリームなど甘いものは好まず,あきらめかけていたところ,患者の口から「おにぎり」と訴えられ,いきなり固形食のおにぎりから開始した.G氏はVF所見でグレード4であり,「楽しみとして,おやつ程度の摂食は可能.栄養摂取は非経口」レベルであったことから,少しづつ量を増やしていき成功した.このように患者の嗜好とVF所見とを照合しながら,柔軟に進めていくのがよいと思われる.
6 摂食・嚥下の第1段階は食べ物を認知する段階(先行期)である.意識障害や重度の認知症の場合,この先行期や食べることへの意欲の面で訓練が困難である.そのため,簡単な会話や指示が理解でき,職員と意思疎通を図ることができるかどうかもポイントであった.また,自分で食べられることも成功の要因のひとつである.私たちはOTやPTの助言を得ながら,訓練時の姿勢や体位・食事用具の工夫などを摂食・嚥下訓練条件表に記載し,できるだけ統一した方法で食事動作の自立を図った.
7 経口摂取能力の回復に伴い,程度に差はあるものの,9例の全てに認知機能の改善がみられた.特にI氏の場合は,経口摂取しなくなったことにより廃用症候群が進行し,ADL全般の機能低下を来たしていた.しかし,運動麻痺や言語障害がなかったため,訓練により職員との関わりがふえたことも刺激となって,運動機能やコミュニケーション能力が回復し,ADL全般の改善へとつながったと考える.
Ⅴ.結論
1.胃瘻であっても,経口摂取能力を取り戻すことができる.
2.人間の再生能力は素晴らしく,90歳を超えても、また胃瘻での栄養摂取が2年に及んでも、経口摂取に成功するケースがある.
3.成功の要因として,VF所見で藤島のグレードが2以上であり、簡単な会話や指示を理解し意思表示できること。および,訓練食を患者に合わせて柔軟に対応することがあげられる.
4.非経口栄養により認知症が進行したケースでは,経口摂取能力の回復に伴い,認知機能の改善やADLの向上が期待できる.
おわりに
経口摂取しなくなるということは,その人のQOLを著しく低下させてしまうことにつながりかねない.
当院では地域の医療機関に安易に胃瘻を造らないよう,また胃瘻造設後はできるだけ早期に紹介していただくよう呼びかけている.
参考文献
1)藤島一郎:よくわかる嚥下障害,永井書店,2001
2)藤島一郎,清水一男:口から食べる嚥下Q&A,中央法規出版,2002
3)逢坂悟郎:摂食・嚥下障害対応における標準化の試み,病院新時代,vol.23,p4-6,2006
4)阪口英夫:口腔機能向上には各職種がそれぞれの役割を果たすことが大切,ロング・ターム・ケア,第14巻1号,p21-27,2006
5)柴尾慶次:「食生活」改善への足がかり,おはよう21,第15巻5号,2004
6)杉橋啓子,杉山みち子,原口洋子:食生活からの自立支援,おはよう21,第12巻14号,p17-36,2002
7)寺岡加代:口腔ケアの大切さ,おはよう21,第15巻8号,p12-17,2004